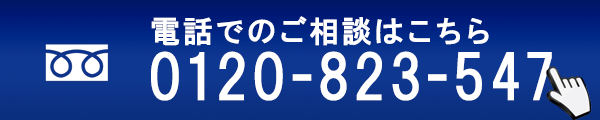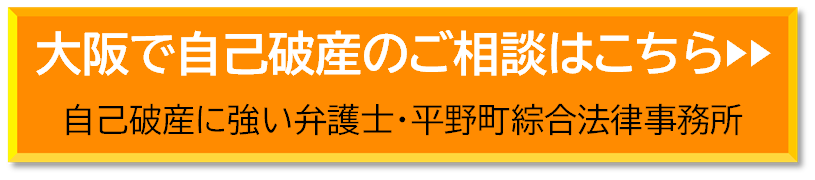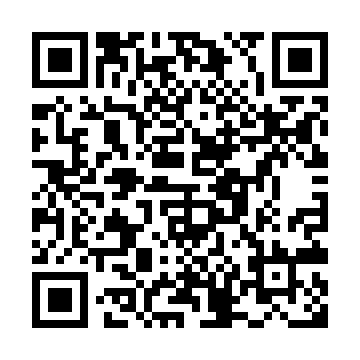個人再生のメリットとデメリットは何ですか?|個人再生が向いているケース、自己破産や任意整理との違いについても解説
個人再生は債務整理の方法の一つであり、個人再生をすれば、借金を大幅に減額することができます。
また、自己破産では持ち家の処分が避けられませんが、個人再生では持ち家は残したまま、住宅ローン以外の借金を減額することができます。
もっとも、個人再生では、自己破産と異なり借金がゼロにはならず、借金を5分の1から10分の1に減額し、3年から5年程度で返済していくことになります。
また、個人再生では、官報に氏名および住所が掲載されたり、ブラックリストに載るなどのデメリットもあります。
そこで、この記事では個人再生のメリット・デメリットを解説し、自己破産や任意整理との違いも詳しく解説していきます。
個人再生を選択すべきか迷っている方は、是非参考にしてみてください。
・個人再生とは?
・個人再生のメリット
・個人再生が向いている人の特徴
・個人再生のデメリット
・個人再生と自己破産の違い
・個人再生と任意整理の違い
・個人再生のメリットとデメリットのまとめ
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所から再生計画の認可決定を受け、住宅ローンを除く借金を5分の1〜10分の1に減額し、減額された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。
個人再生では、減額された借金を原則3年かけて分割して支払うことで、残りの借金については支払義務がなくなります。
個人再生の種類
個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
それぞれの違いは下記の通りです。
なお、小規模個人再生の方が借金の減額率が低くなることが多いので、ほとんどのケースでは小規模個人再生が選択されています。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 給与所得者・自営業者 | 給与所得者のみ |
| 弁済額 | 以下の①~③のうちいずれか高い金額 ①最低100万円 ②借金総額の10~20%(借金総額による) ③現在もっている財産の清算価値 |
以下の①~④のうちいずれか高い金額 ①最低100万円 ②借金総額の10~20%(借金総額による) ③現在もっている財産の清算価値 ④可処分所得の2年分 |
| 債権者の同意 | 債権者の半数又は債権総額の半額を占める債権者が再生計画案に反対した場合には、手続きは廃止 | 債権者の同意不要 |
個人再生の最低弁済額を決める基準のうち、「清算価値」とは、簡単にいうと所有する財産価値の合計です。
個人再生では、少なくとも現在持っている財産の価値(清算価値)以上の金額を弁済しなければなりません(上記③の基準)。
これを「清算価値保障原則」と言います。
そこで、例えば、現在の借金総額が600万円、現在もっている財産の清算価値が200万円の場合を見てみます。
この場合、上記②の基準では、最低弁済基準額は600万円の20%である120万円になりますが、200万円の価値がある財産を所有しているため、上記③の基準(清算価値保障原則)により、200万円の返済が必要となります。
そのため、弁済総額は200万円となります。
給与所得者等再生の場合、最低弁済額を決める基準として、弁済総額が「2年分の可処分所得」以上であることも求められます(小規模個人再生ではこの基準は求められません)。
この「2年分の可処分所得」が計算上高くなることが多く、弁済総額も高くなってしまうため、個人再生では、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生が選択されることが多くなっています。
他方で、小規模個人再生では、債権者の半数又は債権総額の半額を占める債権者が再生計画案に反対した場合には、手続きは廃止されます。
給与所得者等再生では、債権者の同意は不要ですので、債権者の意向にかかわらず手続きを進めることができます
そのため、多数債権者の反対が予想される場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択することになります。
個人再生の要件
個人再生で、再生計画の認可決定を受けるには、次の4つの要件を満たす必要があります。
1. 将来的に継続又は反復した収入を得る見込みがあること
2. 住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であること
3. 債権者からの反対で、書面決議が否決されないこと(小規模個人再生のみ)
4. 過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと(給与所得者等再生のみ)
このように、個人再生には、借金を5分の1から10分の1に減額するというメリットがありますが、法律上厳格な要件が定められています。
個人再生を利用できるかどうかは判断が難しい場合もありますので、詳しくは個人再生に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
個人再生のメリット
個人再生には、次のようなメリットがあります。
・借金を5分の1〜10分の1まで減額できる
・マイホーム(住宅)を残せる
・借金の理由は問われない
・資格・職業の制限がない
・車を残せる場合がある
・受任通知により貸金業者からの催促が止まる
借金を5分の1〜10分の1まで減額できる
個人再生では、以下の3つの基準(給与所得者等再生では4つの基準)を比較して最も高い金額が弁済総額になります。
② 負債額から算出する金額(最低弁済額基準) 負債額の10%~20%
③ 財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準)
④ 収入から算出する金額(可処分所得の2年分)(給与所得者等再生のみ))
このうち①②の負債額から算出する最低弁済額は、次のとおりとなります。
【負債額から算出する最低弁済額】
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額返済(減額なし) |
| 100~500万円未満 | 100万円 |
| 500~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1500~3000万円未満 | 300万円 |
| 3000~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
例えば、借金の総額が300万円だった場合、上の表の「100~500万円未満」に該当するため、個人再生による弁済総額は100万円となります。
個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減らせることです。
自己破産と異なり、個人再生では借金をゼロにはできませんが、住宅ローンを除く借金を5分の1から10分の1まで減額できます。
ただし、最低弁済額が100万円であるため、借金の総額が100万円未満である場合は個人再生の恩恵を受けられません。
マイホーム(住宅)を残せる
個人再生には、住宅ローンの返済については住宅資金特別条項を定めることができますので、マイホームを残した状態で借金を減額することが可能です。
住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンについては、原則として当初の住宅ローン契約の返済計画で返済することになりますが、再生計画の中で、住宅ローンの返済条件や返済期間を変更することも可能です。
ただし、住宅資金特別条項によりマイホームを残して個人再生するには、以下のとおり一定の条件を満たさなければなりません。
• 住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての借入れ)であること
• 再生債務者(個人再生の申立人)が所有している住宅であること(共有可)
• 再生債務者の居住用の建物であること(建物の床面積の2分の1以上が居住用であること)
• 住宅を住宅ローン以外の借入れの担保にしていないこと
住宅資金特別条項を利用してマイホームを残したい場合には、個人再生に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
借金の理由は問われない
自己破産では「免責不許可事由」が定められており、ギャンブルや浪費などの借金の理由によっては免責許可が受けられない可能性もあります。
個人再生には免責不許可事由がありません。そのため、ギャンブルやFXなどの浪費がある場合でも、要件さえ充たしていれば、再生計画は認可してもらえます。
したがって、ギャンブルやFXによる浪費がひどく自己破産をためらうような場合には、個人再生の利用も検討されるといいでしょう。
資格・職業の制限がない
自己破産の場合、職業や資格に制限があり、破産手続き中は免責確定まで特定の職業に就くことができなくなることがあります。
自己破産で就くことが出来ない職業には、以下のようなものがあります。
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引士、
公安委員会委員、公正取引委員会委員
証券会社の外交員、商品取引所会員、貸金業者、警備員
質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、
信用金庫等の会員・役員、一般労働派遣事業者とその役員
日本銀行の役員、旅行業務取扱管理者
これに対して、個人再生の場合、手続き中であっても職業や資格の制限がないので、仕事ができなくなり収入が途絶える心配がありません。
そのため、自己破産では職業や資格の制限に引っかかってしまう場合は、個人再生による解決を検討するといいでしょう。
車を残せる場合がある
個人再生の場合に車を残せるかどうかは車のローンの有無によって変わってきます。
車のローンが残っていない場合
個人再生の場合は、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車が没収されたり、売却されたりすることはありません。個人再生は自己破産と違い、基本的に財産が処分されるようなことはありません。
ただし、ローンがない車を持っている場合は、前述した「清算価値保障原則」により、再生債権の返済総額が上がってしまう可能性があります。
価値の高い車が再生債務者の財産の総額(清算価値)を押し上げることにより、再生債権の返済総額が上がってしまうためです。
車のローンが残っている場合
個人再生も自己破産と同じく、車のローンが残っており所有権留保がある場合については、車はローン会社に引き揚げられますので、原則として車を手元に残すことはできません。
ただし、個人再生の場合は、債務者が車を継続使用できないと、その後の事業継続が困難となり、再生計画による返済ができなくなるような場合は、ローン会社と別除権協定を締結することにより車を残せる場合もあります。
例えば、個人タクシーや個人の運送業者などで、自分の車を直接仕事に使っている場合などが想定できます。
別除権協定が認められる場合はかなり例外的な場合となりますが、車を使う事業者の方で事業を続けながら個人再生を進めたい方は弁護士に相談してみるといいでしょう。
受任通知により貸金業者からの催促が止まる
弁護士や司法書士からの受任通知発送後は、貸金業法21条1項9号により、貸金業者から取り立てをすることは禁止され、依頼者(債務者)が貸金業者と直接に話をすることはありません。
弁護士の受任通知の発送により、貸金業者の督促や取り立てから解放されることは個人再生や自己破産の大きなメリットです。
※参考:貸金業法|e-Gov法令検索個人再生が向いている人の特徴
個人再生のメリットを踏まえると、個人再生が向いている方の特徴は次のとおりです。
• 自己破産では制限をうける職業の人(士業、金融関連業、警備員、保険外交員など)
• ギャンブルや浪費による借金がある人
• マイホームを残したい人
• 車を残したい人
• 自営業者
個人再生か自己破産のどちらを選ぶべきか迷う場合は、それぞれの手続きのメリット・デメリットを弁護士に相談すると良いでしょう。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、主に以下の通りです。
• 最低でも100万円は返済する必要がある
• ブラックリストに載る
• 官報に氏名・住所が掲載される
• 手続きする債務を選べない
• 保証人や連帯保証人に迷惑がかかる
• 手続きが複雑で手間と時間がかかる
• 税金や罰金などは減額されない
以下では、それぞれ解説していきます。
最低でも100万円は返済する必要がある
自己破産ではすべての借金の支払義務が免除されますが、個人再生では借金の返済義務は完全にはなくなりません。
個人再生では借金総額を大幅に減額できるものの、先述した最低弁済額の表のとおり、最低でも100万円は返済する必要があります。
分割返済の期間は3年~5年ですが、原則として3年の分割返済となります。
借金を減額しても返済が難しい場合には、個人再生ではなく、借金がゼロになる自己破産も検討すると良いでしょう。
ブラックリストに載る
個人再生は債務整理手続きの一種となるため、いわゆる「ブラックリスト」に載ります。
いわゆる「ブラックリスト」とは、正式な名称ではなく、信用情報機関に事故情報(債務整理、長期延滞、自己破産など)が記録されている状態を指します。日本には主に「CIC」「JICC」「KSC」という3つの信用情報機関があり、これらの情報は金融機関やカード会社が共有し、審査に活用されます。
ブラックリストに載ると、金融機関やカード会社のサービスがほぼ全て受けられなくなります。
具体的には、
▷ クレジットカードの使用・作成や新たな借入れができなくなる
▷ 賃貸住宅の契約の審査に通らない可能性がある
▷ 携帯電話・スマートフォンの分割購入ができなくなる
などの影響があります。
もっとも、事故情報は、一度登録されたら永遠に登録されているというわけではありません。個人再生の場合は、約5~7年程度で事故情報が削除されます(起算点や期間は、信用情報機関ごとに異なります)。
※CIC (株式会社シー・アイ・シー)のHP※JICC (株式会社日本信用情報機構)のHP
※KSC (全国銀行個人信用情報センター)のHP
官報に氏名・住所が掲載される
個人再生をすると、再生債務者の氏名や住所といった個人情報が「官報」に掲載されることになります。
官報は、国の発行する機関誌のことで、現在では紙面だけではなく、インターネットでも官報を読めるようになっています。
個人再生をすると、以下のタイミングで官報に氏名および住所が掲載されます。
1. 再生手続開始決定時
2. 再生計画案の書面決議または意見聴取時
3. 再生計画認可決定時
しかし、実際に官報を見ているのは、税務署や信用情報機関、金融業者など一部の人だけであり、一般の人が官報を見ることはほぼありません。
そのため、官報に氏名や住所が掲載されたことをきっかけに、家族や知人、勤務先に個人再生をしたことが知られることはほとんどありません。
それでも官報に自分の情報が載るのは絶対に避けたいと考える場合には、個人再生ではなく任意整理を検討すると良いでしょう。
手続きする債務を選べない
個人再生は任意整理と異なり、手続きする債務を自分で選ぶことはできず、すべての債務が対象になってしまいます。
そのため、下記に当てはまる借金がある場合、個人再生ではなく任意整理を検討しても良いでしょう。
・個人間の借金
・勤務先からの借金
・保証人が付いている借金
車やバイクのローンが残っている状態で個人再生の手続きをした場合、車やバイクを手元に残せない可能性もあります。
他方で、任意整理の場合は、財産を処分されることはないので、任意整理しても車やバイクを処分されることはありません。
知人や勤務先からの借金や保証人が付いている借金についても、個人再生ではこれらの借金を除くことはできず、知人や勤務先、保証人に迷惑を掛ける結果になることも多いでしょう。
他方で、個人再生と違い、任意整理では対象となる借金を自分で選ぶことができます。
保証人や連帯保証人に迷惑がかかる
主債務者が個人再生をした場合、主債務者の債務は5分の1から10分の1に減額されます。
もっとも、個人再生はあくまで個人単位の手続きであるため、主債務者が個人再生しても、連帯保証人の債務は減額されません。
つまり、主債務者が個人再生をしても、連帯保証人は債務全額の弁済を求められる立場に変わりはないことになります。
そのため、保証人や連帯保証人に絶対に迷惑を掛けられないという場合は、個人再生ではなく任意整理を選択することを検討すべきでしょう。
手続きが複雑で手間と時間がかかる
個人再生は自己破産同様に裁判所への申立てが必要であり、手続きには手間と時間がかかります。
個人再生はほかの債務整理に比べても、複雑な手続きであり、手間と時間がかかります。
個人再生では、裁判所に再生計画案を提出するなどの手続きも必要ですし、銀行口座の履歴や給与明細、課税資料や家計収支の資料の提出も必要です。
これらの資料に基づき、再生計画案の履行可能性(弁済見込み)を積極的に説明する必要があります。
そのため、個人再生を行う際には債務整理に詳しい弁護士などへの相談するのが良いでしょう。
税金や罰金などは減額されない
個人再生では、すべての借金が債務整理の対象ですが、税金など一部の債務は減額対象になりません。減額対象にならない債務の具体例は以下のとおりです。
• 税金
• 社会保険料
• 将来の養育費
• 罰金
• 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
上記の債務は、個人再生をしても減額されませんので、個人再生の手続き後も継続して支払わなければなりません。
個人再生と自己破産の違い
債務整理には、個人再生のほかに自己破産、任意整理という方法があります。
まず、個人再生と自己破産の違いについて解説します。
自己破産とは、多額の借金を抱えた個人や法人(会社)が、自ら裁判所へ破産の申立てをし、借金や財産を清算したうえで、残った借金の返済が免除(免責)される手続きのことを言います。
要するに、自己破産とは、手持ちの財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにする手続きです。
個人再生と自己破産の一番大きな違いは、個人再生では借金が5分の1から10分の1に大幅に減額されますが、ゼロにはならないことに対し、自己破産では借金がゼロになることです。
他方で、自己破産では、個人再生のように住宅を残すことはできません。
また、自己破産では、浪費などの免責不許可事由が審査されますが、個人再生では借金の理由を問われることはありません。
個人再生と自己破産の比較は以下の表のとおりです。
【個人再生と自己破産の比較】
| 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 借金の減額幅 | 1/5~1/10まで減額 | 原則全ての借金の支払いが免除される。 |
| 住宅に対する影響 | 住宅資金特別条項により残すことができる。 | 住宅は破産管財人による処分や競売により残せない。 |
| 借金の理由(免責不許可事由の有無) | 借金の理由は問われない。 | 浪費などが免責不許可事由になる。 |
| 資格・職業の制限 | なし | 手続き中、一部の資格、職業が制限される。 |
| 安定した収入の見込み | 必要 | 不要 |
なお、個人再生も自己破産も、ブラックリストに載ること(信用情報に事故情報が載ること)、官報に掲載されること、保証人に影響が出るといったデメリットについては、変わりはありません。
個人再生と任意整理の違い
任意整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直して和解をする制度を言います。
任意整理では、利息制限法所定の利息の範囲内の取引であれば、元金が減ることはありませんが、将来の利息が付かないように和解することにメリットがあります。
(※:金融機関によっては将来利息や遅延損害金をカットできないこともあります)
例えば、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないように和解することになります。
一方で、個人再生では、借金が5分の1から10分の1に大幅に減額されることが最大のメリットですが、手続きする債務を選べず、手続きが複雑で手間と時間がかかるというデメリットもあります。
そのため、例えば、知人や勤務先からの借金や保証人が付いている借金について、知人や勤務先、保証人に迷惑を掛けられないので、債務整理の対象から除きたい場合は、個人再生ではなく、任意整理を選択することになるでしょう。
なお、任意整理も個人再生も、ブラックリストに載ること(信用情報に事故情報が載ること)については、変わりはありません。
個人再生のメリットとデメリットのまとめ
個人再生では、借金を5分の1から10分の1に減額され、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を残すことができるというメリットがあります。
もっとも、個人再生をすれば借金を大幅に減額できますが、自己破産と異なり借金の返済義務が完全になくなるわけではありません。
また、任意整理と異なりすべての債務を対象にする必要がありますし、裁判所に申立てをするので手間と時間がかかります。
債務整理の方法としては、個人再生の他、自己破産や任意整理があり、どの手続きを選択することが適切かはケースバイケースです。
そのため、個人再生やその他の方法で迷われている方は、個人再生や債務整理に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
(記事公開日 2025.11.9)