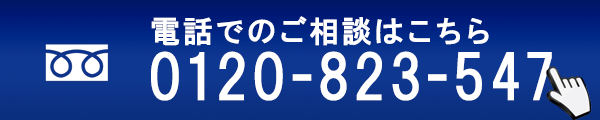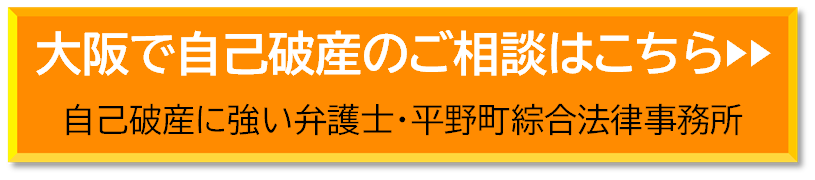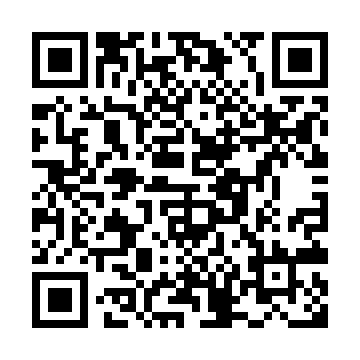自己破産すると滞納している税金はどうなりますか?|税金を支払えないときの対処法も解説
自己破産を検討されている場合、住民税や国民健康保険料といった税金の支払いを滞納されている方も少なくないでしょう。
そして、自己破産をすると、借金とともに滞納している税金についても支払う義務が免除されると考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産をすると滞納している税金はどうなるかについて説明していきたいと思います。
・自己破産をしても、滞納している税金はなくならない。
・非免責債権とは?
・税金は非免責債権となる
・税金の返済は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたらない
・税金の納付義務が免除される場合はあるか?
・税金の時効が成立することはほとんどない
・生活保護受給開始から3年が経過した場合
・税金を滞納するとどうなる?
・税金を支払えないときの対処法
・自己破産と税金のまとめ
自己破産をしても、滞納している税金はなくならない。
自己破産の最大の目的は、最終的に裁判所から免責決定をもらい、借金の返済義務を免除してもらうことにあります。
しかし、破産法では、免責決定が出たとしても返済義務が免除されない債権というものが定められています(破産法253条1項)。これを非免責債権といいます。
非免責債権とは?非免責債権とは、自己破産で裁判所に免責を許可された場合も、支払い義務がなくならない債権のことです。
つまり自己破産をすると借金は帳消しになり支払義務がなくなりますが、非免責債権とされるものは帳消しにならず、支払義務が残ることになります。
非免責債権は破産法第253条1項に定められており、次のようなものがあります。
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権
・雇用関係に基づいて生じた従業員の給料債権など
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権
※非免責債権(破産法253条1項)の条文については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。
税金は非免責債権となる
破産法253条1項において、租税等の請求権は非免責債権であるとされています。尚、租税等の請求権とは、国や地方自治体が行う税金等の請求権のことをいいます。
該当する税金には、次のようなものがあります。
●贈与税
●相続税
●自動車税
●住民税
●固定資産税
●国民健康保険料
●国民年金保険料
●下水道料金
これらの税金を滞納している場合、自己破産により免責決定が出たとしても、帳消しにはならず、支払う必要があります。
税金の返済は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたらない
自己破産では、特定の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として禁止されています。
例えば、金融機関には支払わず、自己破産の直前に勤務先や親族にだけ返済するような行為は偏頗弁済として禁止されます。
偏頗弁済は免責不許可事由にもなります(破産法252条1項3号)。
しかし、滞納している税金だけを支払うことは「偏頗弁済」に該当しません。他の借金を差し置いて、税金だけを返済しても、自己破産には影響ありません。
税金の納付義務が免除される場合はあるか?
では、自己破産以外の方法で、税金の支払義務がなくなる場合があるでしょうか?
これについては、時効が成立する場合と生活保護を受給している場合が問題となります。
以下で詳しく解説していきます。
税金の時効が成立することはほとんどない税金にも、借金などと同じように時効(消滅時効)があります。
消滅時効とは、一定の期間の経過によって、その権利が消滅する制度です。
税金については、納付期限から5年で時効になります。
つまり、税金を支払わないまま5年間が経過すれば、その権利は消滅する可能性があるということです(なお、健康保険料については5年より短い2年です。)。
しかし、税金の時効が成立することはほとんどありません。
なぜなら、消滅時効には、更新や完成猶予という制度があります。
「時効の更新」とは、これまで進んできていた時効期間が0に戻り、また最初から時効期間が始まることをいいます。
「時効の完成猶予」とは、0には戻らないものの、時効期間がストップすることをいいます。
税金を滞納している場合、国や地方公共団体は消滅時効が完成しないように更新や完成猶予の措置をとってきます。
具体的には、税金の督促や交付要求がなされた場合、時効の更新によりまた最初から時効期間の起算が始まることとなります(国税通則法73条)。
税務署が、時効期間が経過するまでの間に督促や交付要求を全くしないというのはまず考えられません。
したがって、税金については、時効が成立して税金の支払いを免れることはまずないと考えてもらった方がよいでしょう。
※税金の時効の完成猶予及び更新(国税通則法73条)の条文については、“e-Gov法令検索「国税通則法」のページ”をご覧ください。
生活保護受給開始から3年が経過した場合
これまで述べたとおり、税金の支払義務がなくなる可能性はほとんどありません。
しかし、生活保護の受給が開始されると、滞納分の督促や、財産の差押え等の滞納処分が一時的に停止されます。
また、生活保護受給が開始されてから3年が経過すると、滞納分の税金の支払い義務が免除されます(国税徴収法153条)。
ただし、この場合も、生活保護の受給から3年の間に生活保護の対象外になれば、再び税金の滞納分の支払い義務が生じるので、注意が必要です。
税金を滞納するとどうなる?
税金を納期限までに納めずに滞納し、税務署や市町村役場からの督促や催告を無視し続けると、場合によっては滞納処分の対象となります。
滞納処分とは、税金滞納者に対し、税務署や市町村役場が強制的に税金の徴収を図る手続きのことです。本来であれば、裁判所が決定する差押えなどの手続きを、課税している行政が自ら行うことができるという強力な権限が与えられています。
差押えの対象となるものは、給料、預貯金、不動産、自動車、売掛金などといったあなたの財産と考えられるものすべてです。
会社に勤めていらっしゃる方の場合、ある日突然、勤務先に連絡がきて給料が差押えられるということになる可能性があり、生活に大きな支障をきたすことにもなります。
税金を支払えないときの対処法
税金を支払えずに放置すると、給料の差押えなどを受け、さらに事態が悪化してしまいます。
そのため、税金は支払えない場合も放置せずに、次のような対処法を取るべきでしょう。
まずは、ご親族に事情を話し、税金を支払うための経済的援助をしてもらうことが考えられるでしょう。
自己破産をしても税金は免除されないということをきちんと説明して、援助をしてもらえうないかをご親族に頼むといいでしょう。
税金が支払えない場合は税務署や市町村役場で相談する。
税金の支払いがどうしても難しい場合は、早めに税務署や市町村役場に相談しましょう。税金を支払う意思はあっても、家計が苦しく、支払うことが困難である事情を話せば、分割での納付(分納)が認められることがあります。
また、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、税金の全額負担が困難であると認められる場合には、住民税などについて減額・免除申請が認められることもあります。
ただし、自己破産の前に、税務署や市町村役場に対し、自己破産を検討していることを話すかどうかについては、注意が必要な場合もあります。
税務署や市町村役場は、自己破産の開始決定前に財産の差押え手続きをしようとすることがあるからです。
そのため、自己破産の前に、税務署や市町村役場に税金の相談に行く際には、事前に弁護士などの専門家にも相談するといいでしょう。
以上のようなことを踏まえ、税金を滞納されている場合は、早めに税務署や市町村役場に相談するようにしましょう。
生活保護を受給する
先ほど述べたとおり、生活保護の受給が開始されると、滞納分の督促や、財産の差押え等の滞納処分が一時的に停止されます。
また、生活保護受給が開始されてから3年が経過すると、滞納分の税金の支払い義務が免除されます。
このように税金の支払いを免れるということも有用だと思いますが、生活費を捻出できない状況を改善できるという意味でも、生活保護を受給することは選択肢の一つになると考えられます。
自己破産と税金のまとめ
今回は、自己破産をすると滞納している税金はどうなるかについて説明しました。
税金は、一般的な借金とは異なり、非免責債権となります。そのため、自己破産をしても、滞納している税金の支払いを免れることはできません。
また、税金滞納分を支払えないからといって放置していると、場合によっては、財産の差押えが執行されます。そうなると、生活に大きな支障をきたすことになるため、早めの対処が必要です。
早めに税務署や市町村役場に相談し、分割での納付を認めてもらったり、事情によっては、住民税などの減額・免除申請をすることが望ましいでしょう。
税金を滞納しなければならないほどの借金でお悩みの方は、早めに弁護士にも相談して、借金問題を解決することをおすすめします。
(記事更新日 2025.5.4)