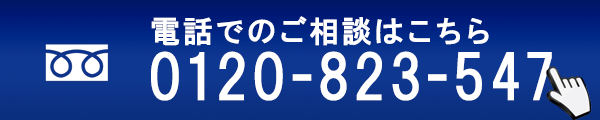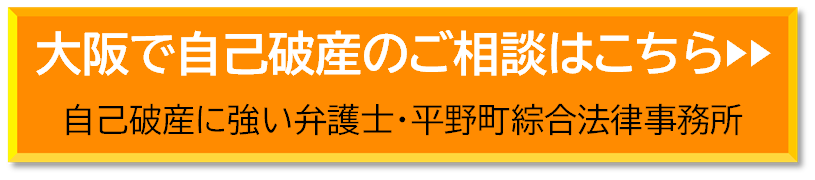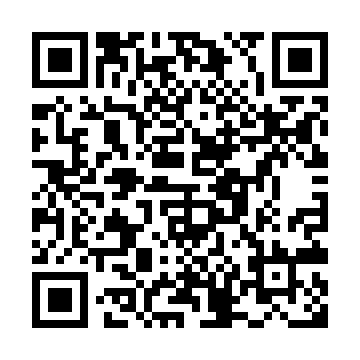自己破産すると家はどうなる?|住宅ローンを払えない場合の競売や任意売却、家を残す方法についても解説
「自己破産すると今住んでいる家から引越しする必要がありますか?」
「家を残したまま、自己破産をする方法はありませんか?」
自己破産すると、原則として持ち家を手放す必要があります。
そのため、せっかく手に入れたマイホームを失いたくないと思い、自己破産に踏み切れない方もいらっしゃると思います。
もっとも、自己破産した場合でも、ご親族に家を買い取ってもらったり、リースバックという方法を利用して、家に住み続けられる場合もあります。
また、どうしても家を手放したくないという場合は、個人再生や任意整理など自己破産以外の方法を利用すれば、家を手放すことなく、借金問題を解決できる可能性もあります。
この記事では、自己破産をすると持ち家はどうなるのか、自己破産後も今の家に住み続ける方法や自己破産以外の債務整理によって家を残す方法について詳しく解説していきます。
自己破産をしたいけど、家を手放すことに不安がある方は是非参考にしてみてください。
・自己破産での持ち家の取り扱い
・自己破産手続きの種類(同時廃止と管財事件)
・持ち家があると原則として管財事件になる
・持ち家があっても同時廃止が認められる場合
・持ち家はどのように処分される?
・任意売却とは?
・競売とは?
・持ち家がある人が自己破産をするときの注意点
・家の名義を勝手に変更してはいけない
・家を不当に安く売却してはいけない
・自己破産後も今の家に住み続ける方法
・親族に家を購入してもらう
・リースバックを利用する
・自己破産以外の債務整理により家を残す方法
・個人再生による解決
・任意整理による解決
・自己破産と持ち家のまとめ
自己破産での持ち家の取り扱い
結論から言うと、自己破産をすると持ち家を手放すことになるのが原則です。
ただ、自己破産の手続きの種類によって持ち家の処分の流れが変わってきますので、まずは自己破産の手続きの種類(同時廃止と管財事件)とそれぞれの場合の持ち家の取り扱いについて解説します。
自己破産手続きの種類(同時廃止と管財事件)
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件があります。
同時廃止とは?
自己破産をする人に財産がほとんどない場合(生活に必要最低限の財産しかない場合)、債権者に財産を分配することはできません。
そのため、裁判所は破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をします(廃止とは終了という意味です)。これを「同時廃止」と呼びます。
同時廃止は基本的に書面審査で手続きが完了する簡便な手続きであり、費用も比較的安く済みます。
よって、できる限り同時廃止で自己破産の申立てをすることが、破産者にとっても負担が少ないと言えるでしょう。
管財事件とは?
破産する人にある程度の財産があり、同時廃止で手続きを進めることができない場合(財産の金額が同時廃止の基準を超える場合)は、破産管財人が選任される管財事件として自己破産の申立てをします。
管財事件の場合は、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなど、同時廃止と比べてやや複雑な手続きとなります。
また、破産手続きの費用も、破産管財人の予納金が必要とされるなど、管財事件では同時廃止よりも高額になります。
持ち家があると原則として管財事件になる
持ち家は一般的に高額な財産になりますので、自己破産をする方に持ち家がある場合は、同時廃止では自己破産ができず、原則として管財事件となります。
そして、不動産は自己破産しても手元に残すことができる自由財産とは認められませんので、持ち家は破産管財人によって売却されることになります。
破産管財人が売却できなかった持ち家については、住宅ローンを貸している金融機関が競売の申立てをすることになります。
そのため、自己破産後はご自宅を手放すことになり、住み続けることはできなくなるのが一般的です。
持ち家があっても同時廃止が認められる場合
持ち家に住宅ローンの抵当権が設定されていて、残りの住宅ローンがその持ち家の価値を大幅に上回っている状態(オーバーローン状態)であれば、同時廃止となることもあります。
オーバーローンが明らかな場合には、抵当権の実行(競売)による売却代金の全額が住宅ローン債権者に優先的に返済され、他の債権者の配当に回ることはありません。
このように破産申立時点で他の債権者の配当に回らないことが明らかであれば、わざわざ破産管財人を選任することは無意味ですので、同時廃止の手続きで自己破産をすることが認められます。
どの程度の住宅ローンがあれば、管財事件ではなく同時廃止が認められるかは、各裁判所の運用に委ねられています。
例えば、大阪地方裁判所では、住宅ローンの残額が、不動産の固定資産評価額の2倍を超えるときは、同時廃止での申立てが認められます。
同時廃止にしてもらえれば、破産管財人の費用が必要ないので、その分費用も安く済み、自己破産の手続きも比較的簡単なものになります。
もっとも、同時廃止になっても、破産手続きとは別に、住宅ローン債権者(抵当権者)によって持ち家の競売の申立てがされることになります。
または、破産者自身が、住宅ローン債権者の同意を得ながら、持ち家を任意売却することになります。
そのため、持ち家がオーバーローンのため、破産手続きが同時廃止になったとしても、やはり競売や任意売却によって持ち家を処分することになり、住み続けることはできなくなるのが一般的です。
持ち家はどのように処分される?
持ち家を所有している方が自己破産をする場合、「任意売却」または「競売」によって持ち家は処分されることになります。
任意売却は、管財事件であれば破産管財人が行い、同時廃止であれば破産者自身が住宅ローン債権者と相談しながら進めることになります。
競売は、持ち家に住宅ローンの抵当権が設定されている場合、住宅ローン債権者(抵当権者)が申立てをすることが一般的です。
そして、持ち家に住宅ローンの抵当権が設定されている場合、任意売却、競売のいずれであっても、まず住宅ローン債権者が持ち家の売却代金から優先的に弁済を受けることになります。
「抵当権」とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する家や土地に金融機関が設定する担保権のことです。
住宅ローンを借りた人が万が一返済できなくなったときは、「担保」とした家や土地を売って(競売して)優先的に弁済を受けることができる権利のことです。
持ち家の処分としては、まず任意売却ができるかを試すことになりますが、買い手が見つからなければ、任意売却は断念せざるを得ません。
また、売却代金によってどれだけ弁済を受けられるかについて、住宅ローン債権者が同意しなければ、任意売却はできないことになります。
そして、破産管財人や破産者自身が任意売却を断念した場合には、住宅ローン債権者(抵当権者)によって競売の申立てがなされることになります。
任意売却とは?
任意売却とは、競売のように裁判所の手続きを通さず、持ち家を一般市場で売却することをいいます。
前述のとおり、任意売却は、管財事件であれば破産管財人が行い、同時廃止であれば破産者自身が住宅ローン債権者と相談しながら進めることになります。
一般的には、競売よりも任意売却の方が手続きが簡単であり、持ち家を高額で売却できる可能性があるため、まずは任意売却による持ち家の処分を進めることが多いでしょう。
任意売却の流れ
以下では、破産管財人による任意売却の流れをご紹介します。
① 破産管財人との面談裁判所は、破産手続開始決定と同時に、「破産管財人」を選任します。
破産管財人は破産者から、建物の鍵や不動産権利証等の書類を引き継ぎます。
破産管財人は、裁判所により選任され、破産者の財産の管理・換価や債権者に対する配当等の手続きを行います。
現在の実務では、経験年数などの一定の条件を満たす弁護士の中から選任されています。
-e1617336579726.png)
破産管財人は不動産の売却に必要な書類が揃うと、不動産業者に依頼して、物件の査定を始めます。
-e1617336579726.png)
不動産を任意売却するためには、不動産に設定されている抵当権を全て抹消する必要があります。
そのため、物件の査定結果が出ると、破産管財人は、抵当権を有する債権者から任意売却の同意を得るため、売出し価格等について交渉を始めます。
-e1617336579726.png)
買主が見つかり、売買代金等について債権者(抵当権者)の同意が得られた場合には、破産管財人は買主と売買契約を締結します。
-e1617336579726.png)
売買契約の締結後、売買契約に定められた条件で代金の支払い及び物件の引渡しがされることになります。
売買代金の大部分は債権者(抵当権者)に支払われ、売買代金の一部(数%)を破産財団に組み入れることが一般的です。
これにより破産管財人による任意売却は完了します。
競売とは?
競売とは、不動産を強制的に売却し、売却代金を債務の返済や債権者への配当に充てる裁判所の手続きをいいます。
前述のとおり、破産者の持ち家の処分としては、まず任意売却ができるかを試すことになります。
しかし、任意売却によって買い手が見つからない場合や売却代金による弁済額について住宅ローン債権者(抵当権者)が同意しなければ、任意売却はできないことになります。
任意売却がうまく行かない場合、住宅ローン債権者(抵当権者)は担保不動産の競売申立てをすることになります。
競売の流れ
以下では、競売の流れをご紹介します。
① 競売の申立て債権者(抵当権者)が裁判所に対し、競売の申立てを行います。
-e1617336579726.png)
裁判所は、申立てが適法にされていると認められたときは、不動産競売を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。
-e1617336579726.png)
裁判所は、執行官や評価人に調査を命じて目的不動産について詳細な調査を行い、買受希望者に閲覧してもらうための三点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)を作成します。
現況調査では、自宅の外観だけではなく、自宅の中も写真撮影されることになります。
-e1617336579726.png)
物件の現況調査後、裁判所から競売の期間入札通知書が発送されます。
期間入札通知書には、競売対象物件の入札期間と開札日が記載されています。
-e1617336579726.png)
インターネット上で物件情報が公開され、誰でも競売対象物件の競売についての情報を閲覧することができる状態になります。
-e1617336579726.png)
入札が始まり、入札期間が過ぎると開札され、入札期限までに最も高い値段を提示した者が落札者に決定します。
-e1617336579726.png)
落札者が決定すると、裁判所が売却許可決定を出します。
これにより落札者は買受人となります。
-e1617336579726.png)
買受人が代金を納付すると、物件の所有権は買受人に移転し、債務者は退去日を決めて家を明け渡すことになります。
-e1617336579726.png)
裁判所は、法律上優先する債権の順番に従って、競売された不動産の売却代金を債権者に配当することになります。
競売された場合の退去時期について
競売手続開始決定から退去日が確定するまでの期間は、6か月~1年程度となることが多く、その間は持ち家に住み続けることが可能です。
もっとも、持ち家が競売された場合、買受人が代金を納付後、約1~2か月以内に家を退去しなければならないことになります。
家を退去しないでいると強制的に退去を求められることになります。
そのため、買受人が代金納付後には、すぐに退去できるように早めに住居を確保する必要があります。
持ち家がある人が自己破産をするときの注意点
持ち家はある人が自己破産をするときには、次のような行動に注意すべきでしょう。
家の名義を勝手に変更してはいけない
破産管財人による処分の対象となる財産は、原則として、破産者名義のものに限られます。
そのため、家の名義が家族や知人である場合は、自己破産によって家を処分されることは原則としてありません。
しかし、家の処分を免れるために、自己破産の直前に家の名義を家族や知人に変更することは大いに問題があります。
自己破産の直前に家の名義を変更して隠してしまうことは、「財産隠し」をしたとして、免責不許可事由に該当する可能性があります(破産法第252条1項1号)。
また、家の所有権移転登記を破産管財人によって否認される可能性があります。そうなれば、結局、家の名義は元に戻されて、破産管財人によって処分されることになります。
さらに財産を隠すことは、詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性もあります(破産法第265条1項1号)。
詐欺破産罪になると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、場合によっては、これらの両方が科されることがあります。
不動産の所有名義は登記簿に登記されており、ごまかすことができません。
そのため、自己破産の直前に家の名義を変更して家を隠すことは絶対にしないようにしましょう。
※免責不許可事由の条文(破産法252条)はこちら→破産法 | e-Gov法令検索
家を不当に安く売却してはいけない
自己破産の前に適正な価格で持ち家を売却することは基本的には問題ありません。
その場合、売却代金は優先する住宅ローン債権者(抵当権者)への返済に充てられることになります。
また、持ち家に抵当権が付いていない場合は、諸費用(仲介手数料等)を支払った後の売却代金残額を破産管財人に引き継ぐ必要があります。
しかし、持ち家を市場価格よりも安い価格で売却したり、売却代金を浪費や家族などの特定の債権者のみの返済に充てるなどした場合は、不当な財産減少行為や偏波弁済といった免責不許可事由に当たる可能性があります(破産法252条)。
そのため、自己破産の前に持ち家を売却する場合には、必ず自己破産に強い弁護士に相談しながら進め、後で問題が発生しないように注意すべきでしょう。
自己破産後も今の家に住み続ける方法
自己破産をすると、原則として持ち家を手放すことになります。
しかし、持ち家を失うと、賃貸住宅への引越しや場合によっては転職や転校を余儀なくされることもあり、生活に大きな影響が出ることになります。
そのため、「なんとか今の家に住み続けたい」と思う方もいらっしゃると思います。
そこで、以下では自己破産後も今の家に住み続けることができる2つの方法について解説します。
親族に家を購入してもらう
自己破産後も今の家に住み続ける方法として、自己破産後に破産管財人を通して、親族に一括で家を購入してもらうという方法があります。
重要なのは、①「自己破産後」に②「破産管財人を通して」③「一括」で購入してもらうという点です。
自己破産の前に弁護士などの専門家を通さずに家を売却すると、その価格や売却代金の使途によっては、財産隠しや財産減少行為とみなされ、最終的に借金の免責が認められない可能性もあります。
しかし、自己破産後に、破産管財人を通して親族に家を購入してもらう場合は、破産管財人は裁判所の許可の下、適正な価格で売却を行うため、財産隠しや財産減少行為といった問題は生じません。
そのため、持ち家を親族に購入してもらう場合は、破産管財人を通じて購入してもらうことが安全で望ましいでしょう。
もっとも、親族に家を購入してもらう場合、住宅ローンを利用できないことが多いため、そのような場合には、不動産の購入代金を一括で支払う必要があります。
そのため、親族が住宅ローンを利用できないときは、家の購入代金を現金で一括決済するだけの経済的余裕が必要となってきます。
リースバックを利用する
リースバックとは、家をリースバック事業者(不動産会社など)に売却し、同時にリースバック事業者を貸主として賃貸借契約を締結し、毎月賃料を支払うことで、家に住み続けることができるサービスのことをいいます。
リースバックを利用すると、不動産売却後もその家に住み続けることができます。
ただし、リースバックを利用するには、次の注意点があります。
まず、リースバック事業者に対する家の売却代金は、市場価格に合った適正な価格で売却する必要があります。
持ち家を市場価格よりも安い価格で売却した場合、後に破産管財人により否認される可能性があります。
そのため、リースバック事業者に対する売却についても、破産管財人を通じて契約することが望ましいでしょう。
また、リースバック事業者に支払う家賃は、地域相場とは関係なく、リースバック事業者が決定するため、家賃が高額になるケースも考えられます。
そのため、リースバックを利用する場合は、あらかじめ弁護士などの専門家に相談して、自己破産との関係で問題が生じないか、家賃が高くて生活を圧迫しないかなどを検討する必要があります。
自己破産以外の債務整理により家を残す方法
どうしても持ち家を手放したくないという方は、自己破産以外の債務整理の方法も検討するといいでしょう。
債務整理には、「自己破産」の他、「個人再生」「任意整理」という方法があります。
「個人再生」と「任意整理」の方法によれば、持ち家を失うことなく、借金の整理を進めることができます。
個人再生による解決
個人再生では、住宅ローンの有無によって注意すべき点が変わってきます。
住宅ローンが残っている場合
個人再生とは、住宅ローンを除く借金を原則5分の1に圧縮し(ただし、100万円未満には圧縮できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできない)、圧縮された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。
個人再生は住宅を所有したまま、住宅ローン以外の借金の圧縮を図るのに適した制度と言えます。
個人再生では、住宅ローンの返済について住宅資金特別条項を定めることができます。
住宅ローンについては、原則として当初の住宅ローン契約の返済計画で返済することになりますが、再生計画の中で、住宅ローンの返済条件や返済期間を変更することも可能です。
住宅ローンが残っていない場合
個人再生の場合は、住宅ローンの支払いが終わっていれば、住宅が没収されたり、売却されたりすることはありません。個人再生は自己破産と違い、基本的に財産が処分されるようなことはありません。
ただし、住宅ローンがない持ち家がある場合は、その持ち家(土地建物)の価値が高ければ、再生債権の返済総額が上がってしまう可能性があります。
これは個人再生の「清算価値保障原則」があるためです。
「清算価値」とは、その人が保有している財産のことであり、「清算価値保障原則」とは、個人再生した場合に少なくとも清算価値以上の金額を弁済しなければならないという原則です。
この原則により、不動産が財産の総額を押し上げることにより、再生債権の返済総額が上がってしまうということがあり得ます。
不動産は一般的に高額になるため、無担保の不動産があるような場合は、再生債権の返済総額が高くなりすぎて、個人再生を利用できない場合も多いでしょう。
任意整理による解決
任意整理とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直して和解をする制度を言います。
任意整理では、利息制限法の利息で引き直し計算をして、減額された元本の分割返済を約し、かつ、その元本の分割返済に当たっては将来の利息が付かないように和解することになります。
(※:金融機関によっては利息や遅延損害金をカットできないこともあります)
例えば、利息の引き直し計算の結果、借入元本が50万円残る場合、その50万円を毎月1万円ずつ50回にわたって返済することを合意し、その50回の分割返済中には利息が付かないように和解することになります。
任意整理の場合は、財産を処分されることはないので、任意整理しても持ち家を処分されることはありません。
また、任意整理は自己破産と違い、任意整理の対象となる借金を「選べる」というメリットがあります。
そのため、住宅ローンの返済中の場合は、住宅ローンを任意整理の対象から外し、自力で完済できれば、持ち家を手元に残すことができます。
よって、任意整理による場合は減額された借金の分割返済は続きますが、返済能力と返済する意思があり、住宅ローンを任意整理の対象から外したい場合は、任意整理を検討するとよいでしょう。
自己破産と持ち家のまとめ
自己破産をする場合、持ち家は高額な財産であり、自由財産には含まれませんので、破産管財人による任意売却や競売によって処分されることが原則です。
そのため、基本的には、自己破産によって持ち家を手放す必要があります。
もっとも、自己破産した場合でも、ご親族に家を買い取ってもらったり、リースバックを利用して、家に住み続けられる場合もあります。
また、確実に持ち家を残したいのであれば、自己破産以外の個人再生や任意整理を利用することも考えられます。
持ち家がある場合の自己破産やその他の債務整理には、専門的な知識と経験が必要となります。
そのため、住宅ローンや借金の返済に困り、持ち家のことで悩んでいらっしゃる方は、お早めに自己破産や借金問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
(記事公開日 2025.3.9)