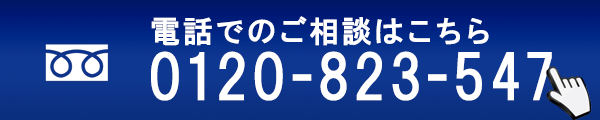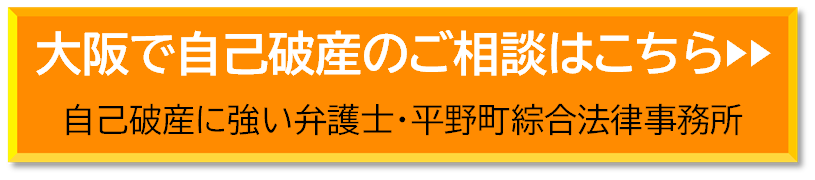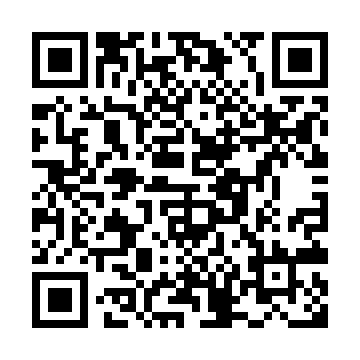自己破産すると年金はどうなりますか?|滞納している年金保険料の取り扱いについても解説
自己破産をすると無一文になり、年金も受け取れなくなってしまうのではと心配な方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、年金は生活を保障するための重要な権利であるため、自己破産をしても原則として年金を受け取る権利を失うことはありません。
ただ、保険会社と契約している個人年金などは解約が必要になる場合もあり得ます。
この記事では、年金受給者の方に対して、自己破産をした場合の年金の取り扱いについて解説しています。
まだ年金保険料を納めている現役世代の方には、自己破産しても滞納している年金保険料は免責されないことについて解説していますので、ぜひご覧ください。
・自己破産をしても受け取ることができる年金
・国民年金・厚生年金・共済年金
・障害年金
・遺族年金
・企業年金
・個人年金は解約しなければならない場合もある
・個人年金とは?
・個人年金を残せる場合と解約が必要となる場合
・すでに受給した年金は現金や預貯金として処理される
・借入れのある銀行の口座を年金口座としている場合は注意が必要
・自己破産しても、滞納している年金保険料は免責されない
・非免責債権とは?
・国民年金等の保険料は非免責債権となる
・国民年金等の保険料の支払いは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたらない
・自己破産と年金のまとめ
自己破産をしても受け取ることができる年金
自己破産すると、自分の財産も処分されることになり、将来の年金も受け取れなくなってしまうのではと心配な方もいらっしゃると思います。
しかし、差し押さえを禁止された財産(差押禁止財産)は、自己破産をしても本来的自由財産として、手元に残すことができます。
そして、年金(特に公的年金)は法律上差し押さえが禁止されているため、自己破産をしても年金を取られてしまうことはなく、年金の受給権を失うことはありません。
以下では、どのような年金が差押禁止財産として守られるかについて詳しく解説します。
国民年金・厚生年金・共済年金
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金は、差押禁止財産に該当するため、自己破産しても、年金を受給することができます。
公的年金は生活をしていく上で最低限必要な財産ですので、自己破産をしても守られることになります。
| 公的年金の種類 | 加入対象者 |
|---|---|
| 国民年金 | 20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入していない人 |
| 厚生年金 | 厚生年金に加入する事業所の会社員等 |
| 共済年金 | 公務員や私立学校教職員 |
障害年金
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)とは、健康状態や能力に障害があるため、生活や仕事が制限されてしまう場合に受給できる年金のことです。
障害年金も差押禁止財産に該当するため、自己破産しても、年金を受給することができます。
遺族年金
遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)とは、国民年金、厚生年金の被保険者(加入者)や被保険者だった方が亡くなった場合に遺族(配偶者など)が受給できる年金のことです。
遺族年金も差押禁止財産に該当するため、自己破産しても、年金を受給することができます。
企業年金
企業年金とは、企業や団体が従業員のために運営する年金制度のことです。
一般的には従業員が雇用されている間に加入し、定年退職後に給付される年金を受け取ることができます。
企業年金は原則、公的年金と同様に差押禁止財産のうちの「差押禁止債権」に該当するため、自己破産をしても処分の対象になりません。
差押禁止債権となる企業年金の例としては、確定給付年金や確定拠出年金などがあり、自己破産をしても、問題なくこれらの年金を受給できます。
個人年金は解約しなければならない場合もある
個人年金は、これまでに述べた公的年金とは異なり、差押禁止財産には該当しませんので、自己破産によって解約が必要となる場合もあります。
個人年金とは?
民間の保険会社と契約している個人年金保険は、お金を積み立てることで将来年金を受け取ることができるという金融商品ですが、こういった商品を途中解約した場合、解約返戻金が発生する場合があります。
解約返戻金とは、個人年金を途中で解約した際に、積み立ててきた保険料や契約期間に応じて、保険会社が保険契約者に返すお金のことをいいます。つまり、個人年金保険の解約返戻金は保険契約者の財産ということになります。
そして、この解約返戻金は、公的年金などと異なり、差押禁止財産には該当しません。
そのため、自己破産をする場合、個人年金を解約し、債務の返済にあてなければならない場合があります。
個人年金を残せる場合と解約が必要となる場合
自己破産とは、手持ちの財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにする手続きです。
ただし、自己破産をすることで、全ての財産を手放し、全く無一文になると生活ができなくなります。
そのため、自己破産をしても、破産者の生活再建のため、最大99万円の財産を所持したまま自己破産することが認められています(これを「自由財産の拡張」といいます)。
そして、個人年金保険の解約返戻金も一定の金額の範囲内では、自由財産の拡張により、保険を解約せず契約を維持することができます。
大阪地裁の取り扱いでは、個人年金保険の解約返戻金が20万円未満であれば、保険を解約せずに残すことができ、同時廃止の手続きで自己破産をすることができます。
解約返戻金が20万円以上の場合は、自己破産の手続きは破産管財人がつく管財事件となります。
管財事件の場合も、個人年金保険の解約返戻金が預貯金等の他の財産と合わせて99万円以内である場合は、自由財産の拡張が認められますので、保険を解約せず、契約を残すことができます。
他方で、個人年金保険の解約返戻金が自由財産(最大99万円)の範囲を超える場合は、破産管財人によって保険が解約され、破産財団に組み入れられる可能性があります。
このように個人年金については、自己破産しても残せる場合と解約が必要となる場合がありますので、詳しくは弁護士に相談するといいでしょう。
※自己破産手続きの種類については、“自己破産手続きの流れについて教えて下さい。|自己破産の種類(同時廃止と管財事件)についても解説”をご覧ください。
すでに受給した年金は現金や預貯金として処理される
すでに受給した年金(銀行口座に振り込まれたもの)については、差押禁止財産である「年金」ではなくなり、「現金」や「預貯金」として処理されます。
大阪地裁の取り扱いでは、(年金が振り込まれた後の)現金及び普通預貯金の合計が50万円以下であれば、同時廃止の手続きで自己破産をすることができます。
現金及び普通預貯金が50万円を超える場合は、自己破産の手続きは破産管財人がつく管財事件となります。
管財事件の場合は、(年金が振り込まれた後の)現預金と他の財産を合わせて99万円以内である場合は、自由財産の拡張が認められますので、それらの財産を手元に残すことができます。
他方で、現預金やその他の財産が自由財産(最大99万円)の範囲を超える場合は、99万円を超える部分については、原則として破産管財人による処分の対象になります。
借入れのある銀行の口座を年金口座としている場合は注意が必要
銀行から借入れをしている場合に、自己破産を受任した弁護士がその銀行に受任通知を発送すると、その銀行の口座は全て凍結されてしまいます。
預金口座の凍結とは、銀行が、預金口座からの出金・送金・引き落とし、口座への入金を制限することを言います。
銀行から借入れをしている場合、その銀行の口座を年金の受給口座にしていると、口座の凍結後には年金が振り込まれなくなるため、一時的に年金を受け取れなくなってしまいます。
そうならないためにも、自己破産の手続きを行う前に年金の振込口座を変更することが重要です。
また、銀行は、自己破産の受任通知によって債務者が借金の返済ができない状態であることがわかると、年金などが振り込まれた預金を引き出せないようにし、預金残高と貸付金を相殺してしまいます。
そのため、凍結される可能性のある口座に年金が振り込まれている場合には、受任通知を発送する前に全額引き出しておく必要があり、注意が必要です。
自己破産しても、滞納している年金保険料は免責されない
ここまでは、年金受給者の方に対して、自己破産をした場合の年金の取り扱いについて解説しました。
ここからは、年金保険料を納めている現役世代の方に対して、自己破産しても、滞納している年金保険料は免責されないことについて解説していきます。
自己破産の最大の目的は、最終的に裁判所から免責決定をもらい、借金の返済義務を免除してもらうことにあります。
しかし、破産法では、免責決定が出たとしても返済義務が免除されない債権というものが定められています(破産法253条1項)。これを非免責債権といいます。
非免責債権とは?
非免責債権とは、自己破産で裁判所に免責を許可された場合も、支払い義務がなくならない債権のことです。
つまり自己破産をすると借金は帳消しになり支払義務がなくなりますが、非免責債権とされるものは帳消しにならず、支払義務が残ることになります。
非免責債権は破産法第253条1項に定められており、次のようなものがあります。
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権
・雇用関係に基づいて生じた従業員の給料債権など
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権
※非免責債権(破産法253条1項)の条文については、”e-Gov法令検索「破産法」のページ”をご覧ください。
国民年金等の保険料は非免責債権となる
破産法253条1項において、租税等の請求権は非免責債権であるとされています。尚、租税等の請求権とは、国や地方自治体が行う税金等の請求権のことをいいます。
「租税」というと、所得税や住民税(市県民税)、固定資産税、自動車税といった税金だけを思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、国民年金などの保険料も租税等の請求権に該当しますので、免責決定により免責されることはありません。
そのため、国民年金などの保険料を滞納している場合、自己破産により免責決定が出たとしても、帳消しにはならず、支払う必要があります。
国民年金等の保険料の支払いは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたらない
自己破産では、特定の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として禁止されています。
例えば、金融機関には支払わず、自己破産の直前に勤務先や親族にだけ返済するような行為は偏頗弁済として禁止されます。
偏頗弁済は免責不許可事由にもなります(破産法252条1項3号)。
しかし、滞納している年金保険料だけを支払うことは「偏頗弁済」に該当しません。他の借金を差し置いて、税金や年金保険料だけを返済しても、自己破産には影響ありません。
自己破産と年金のまとめ
年金は生活を保障するための重要な権利であるため、自己破産をしても原則として年金を受け取る権利を失うことはありません。
そのため、自己破産をしても、差押禁止財産である国民年金や厚生年金などの受給権を失うことはなく、今までとおり年金を受給することができます。
他方で、保険会社と契約している個人年金などは、自己破産により解約が必要になる場合もあり得ます。
まだ年金保険料を納めている現役世代の方については、自己破産をしても滞納している年金保険料は免責されません。
年金保険料の支払いがどうしても難しい場合は、早めに年金事務所や市町村役場の国民年金課に相談すべきでしょう。
また、自己破産によって年金がどうなるかについて不安がある方は、早めに自己破産に強い弁護士に相談することをお勧めします。
(記事公開日 2025.5.15)