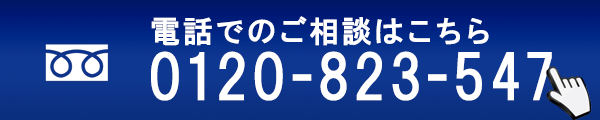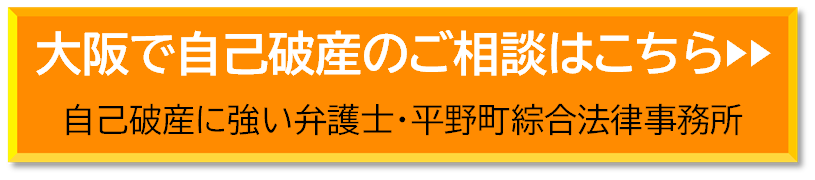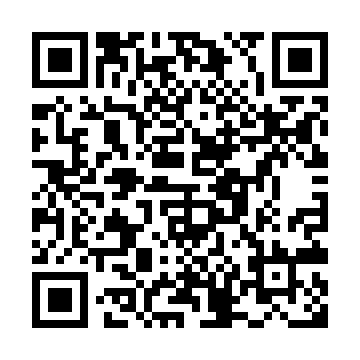自己破産は2回目でもできるのでしょうか?
「過去に自己破産をしているのですが、2回目の自己破産は可能ですか?」という質問をお受けすることがあります。
結論から申し上げますと、自己破産に回数制限はないため、2回目の自己破産は可能です。
ただし、2回目の自己破産をする際には、いくつかの条件を満たす必要があります。また、最終的に免責を許可するかどうかについて、裁判所から1回目の自己破産よりも厳しく審査されることになります。
そこで今回は、2回目の自己破産を検討されている方が知っておくべき条件や注意しなければならないこと、また、自己破産が難しい場合の対処法についてご説明します。
1.2回目の自己破産ができる条件2.2回目の自己破産をする際の注意点
3.2回目の自己破産でも免責を許可してもらうためには?
4.2回目の自己破産が難しい場合の対処法
5.2回目の自己破産のまとめ
1.2回目の自己破産ができる条件
①前回の自己破産から7年以上経過していること
2回目の自己破産をする場合には、原則として、前回の自己破産で免責決定が確定した日から7年以上経過していることが条件となってきます。
過去7年以内の自己破産は、免責不許可事由に該当し、原則として免責されないことになっているためです。
ただし、免責決定が確定した日から7年が経過する前であったとしても、裁判所が2回目の自己破産に至った事情を考慮して、免責を与えることがやむを得ないと判断した場合には、裁判所の裁量によって免責が許可(裁量免責)される場合があります。
たとえば、
1.生活費や医療費のために借金をしたが、病気で働けなくなり、借金を返せなくなってしまった場合
2.リストラにより仕事を失って、借金の返済ができなくなってしまった場合
などは、どうすることもできない特別な事情があると考えられますので、7年以内の再度の自己破産の申立てでも、裁量免責により借金が免除される可能性があるでしょう。
②前回の自己破産と原因が違うこと(特に浪費が原因でないこと)
今回の自己破産に至った原因が前回と同じ場合、裁判所から前回の自己破産について反省していないとみなされる可能性が高いため、免責を許可されるのが難しくなります。
1回目の自己破産であれば、ギャンブルや浪費などといった免責不許可事由があったとしても、裁量免責により免責が許可されることが多いでしょう。
しかし、再び競馬やパチンコにはまったり、収入に見合わない高価な物を購入するなどして借金を増やし、前回の自己破産と同じく、浪費によって2回目の自己破産に至った場合は、裁判所から裁量免責を受けることが難しくなります。
そのため、2回とも浪費が原因で借金を返済できなくなったような場合は、自己破産ができるのか、他の方法で借金を整理する方がいいかについて、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
2.2回目の自己破産をする際の注意点
①管財事件になる可能性が高くなる
自己破産の手続きには、“同時廃止”と“管財事件”という手続きがあります。
※同時廃止、管財事件についてはこちら→「自己破産の手続きの流れについて教えて下さい。」
2回目の自己破産となると、所有している財産が少なくても、自己破産に至った原因や免責不許可事由の有無を調べるために、破産管財人が選任される管財事件となる可能性が高くなります。
管財事件では、破産管財人が選任され、財産の調査を受けたり、日々の生活について指導監督を受けることになります。また、破産管財人に引き継ぐ管財予納金(最低20万5000円)を準備しておく必要があります。
そのため、同時廃止よりも管財事件の方が破産する方にとって負担が大きい手続きになりますが、2回目の自己破産の場合は、1回目よりも管財事件になる可能性は高くなります。
2回目の自己破産では、同時廃止か管財事件になるかは、ケースバイケースですので、自己破産に強い弁護士に相談すべきでしょう。
②費用や手間がかかる
2回目の自己破産ということで管財事件となった場合、弁護士費用に加えて、破産管財人の費用が必要になるため、同時廃止より費用がかかってきます。
さらには、管財事件となった場合、管財人との面談や裁判所で開かれる債権者集会への出頭が必要となり、労力の面でも負担が増します。
また、同時廃止であっても、免責を許可するかどうか裁判所が判断するにあたって、反省文や生活再建策の提出、集団免責審尋期日への出頭などが求められることもあります。
そのため、2回目の自己破産は、1回目よりも、費用や手間がかかる可能性が高くなることは否定できないでしょう。
3.2回目の自己破産でも免責を許可してもらうためには?
①やむを得ない事情があること
2回目の免責を認めてもらうためには、再び自己破産に至ったことについて、やむを得ない事情があると裁判所に納得してもらえるかが重要になってきます。
何度も申し上げているとおり、1回目と2回目の自己破産の原因がどちらもギャンブルや浪費などによるものである場合は、免責が許可されることは難しくなります。
しかし、例えば、1回目はギャンブルにはまって、借金が増えて自己破産したものの、2回目の自己破産は、真面目に働いていたところ、親の病気の治療や介護で借金をせざるを得なかったなどの事情がある場合は、やむを得ない事情があるとして、免責が認められやすくなるでしょう。
②真摯に反省していること
自己破産により免責が許可されると、破産者は借金の返済を免除されることになりますが、反面、債権者は債権を回収できなくなるという不利益を被ります。
自己破産は債権者に多大な迷惑や負担をかけることになるため、破産者は二度と自己破産をしないよう、十分に反省することが求められます。
それにもかかわらず、2回目の自己破産に至ったということは、裁判所から前回の自己破産について真摯に反省していないのではないかと判断されてもおかしくありません。
そのため、2回目の自己破産の手続きにおいては、きちんと反省していることが裁判官に伝わるように、真摯な態度で臨むことが大事になってきます。
4.2回目の自己破産が難しい場合の対処法
1回目の自己破産の原因がギャンブルなどの浪費であり、再度、借金が増えた原因もギャンブルなどの浪費である場合、2回目の自己破産では免責が認められない可能性もあります。
このように2回目の自己破産が難しいと判断される場合には、次のような方法で借金を整理することが考えられます。
①任意整理による解決
“任意整理”とは、サラ金やクレジット会社と任意に交渉して、債務の返済総額や返済条件・期間を見直し和解をする制度を言います。
任意整理では、借入金を原則として3年、最長でも5年の分割払いで返済することになりますが、分割返済期間中には利息が発生しないように、将来の利息を免除してもらったり、一括払いでの返済であれば、過去の遅延損害金を免除してもらうなどの交渉を債権者との間で行います。
ただし、任意整理に応じるかどうかは、あくまでも債権者の意思次第であり、相応の法律の知識が必要となるため、交渉にあたっては、債務整理に関して経験豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
②個人再生による解決
“個人再生”とは、住宅ローンを除く借金を原則5分の1に圧縮し(ただし、100万円未満には圧縮できず、かつ、破産となった場合の予想配当総額を下回ることはできません)、圧縮された借金を原則3年で分割返済する制度を言います。
個人再生には免責不許可事由がありません。そのため、過去に自己破産の経験があり、2回目の自己破産では、浪費などの免責不許可事由により裁量免責さえも認められない可能性がある場合には、個人再生の利用を検討することが望ましいでしょう。
2回目の自己破産のまとめ
いかがでしたでしょうか?
一定の条件を満たせば、2回目の自己破産の申立てであっても、免責決定を受けることは可能です。
しかし、1回目の自己破産に比べ、裁判所から厳しい審査を受けることになり、手続きや費用といった面で負担が大きくなります。
そして、何より、2回目の自己破産で最終的に裁判所から免責の許可を受けるためには、再度の自己破産についてやむを得ない事情があったと裁判官を納得させることや、借金が増えた原因を振り返り、真摯に反省していることが重要になります。
これらを踏まえて、2回目の自己破産が難しいようであれば、自己破産以外の手段(任意整理や個人再生)を検討してみるといいでしょう。
いずれにせよ、自己破産や債務整理の手続きには、専門的な知識と経験が必要になります。
そのため、借金でお悩みの方は、まずは借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。